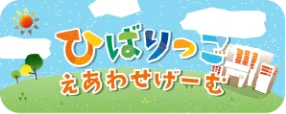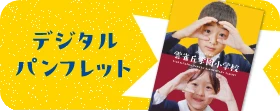算数の学習の中で,算数ならではの面白いところはどこでしょう?
いくつかありますが,その中の一つに「式を読む」活動があると思います。
式は,算数ならではの道具・言語で,式には意味やメッセージが込められています。現在,それを読む活動を6年生の「場合を順序よく整理して」の学習に取り入れています。
単元の導入から数問で,樹形図や表,式を使った考え方を扱い,子どもたちが色々な考える術を持った上で,新たな問題に取り組みました。
問題:「0」,「1」,「2」,「3」のカードが1枚ずつあります。

(1)このカードから2枚を使って2けたの整数をつくります。全部で何通りできますか。
皆さんなら,どのように考えて答えを導き出しますか?
本校の算数の授業では,それぞれがまず自分なりの方法で考える時間を取ります。その後,現在は4人班で考え方を共有し,次に全体の場で共有,最後に理解した方法を全員が2人組でアウトプットするという流れです。
教科書をなぞると,どの問題も1~2つくらいの解法で終わってしまうのですが,教科書を見せずに,子どもたちの自由な発想に任せると,9通りの方法が出て来ました。
そのうち,式での考え方をいくつかご紹介しますので是非,以下の式を読んでみてください。
①3×3=9
②3×4-3=9
③4×3-3=9
④4×4-7=9
⑤3×2+3=9
⑥{2×2×2×2-(1+4+4+1)}×2-3=9
いくつ読むことができましたか?
②や③は,ほぼ同じ式ですが,意味がまったく異なりますね。また,どれも一見とても単純な式ですが,それぞれの数字が表すものは何なのか,なぜその演算を使うのかなど,話し合うテーマは盛りだくさんです。この問題を2時間かけて扱いました。
ちなみに,(2)では3けたに挑戦です。すると,(1)の2けたを応用できないか・・・と考え出す子どもたちの姿がありました。子どもたちの素直な発想は面白いです。
また,6年生にもなると,子どもたちの発想は授業者の予想を上回ってきます。どんな考え方が出るのか予想しきれないときも多々あるので,考え方が出されて即座にすべてが理解できるわけではありません。
教師も,子どもたちと同じように発表を聞いて,理解して,アウトプットしてともに学んでいます。
授業後,休み時間も式について語り合うこともあります。「算数してるな-♪」と実感できる瞬間です。